痛みに関する解剖・生理学
関上 寅之輔上級Conditioning Coach
前回のコラムは、
「痛み」の機能について触れました。
→https://r-body.com/blog/20190318/3153/
今回は、「痛み」に関する
解剖・生理について簡単に説明していきます。
解剖学や生理学と聞くと
難しい気持ちになるかもしれませんが、
カラダの構造がどうなっていて、
どのようなメカニズムがあるのかというお話です。
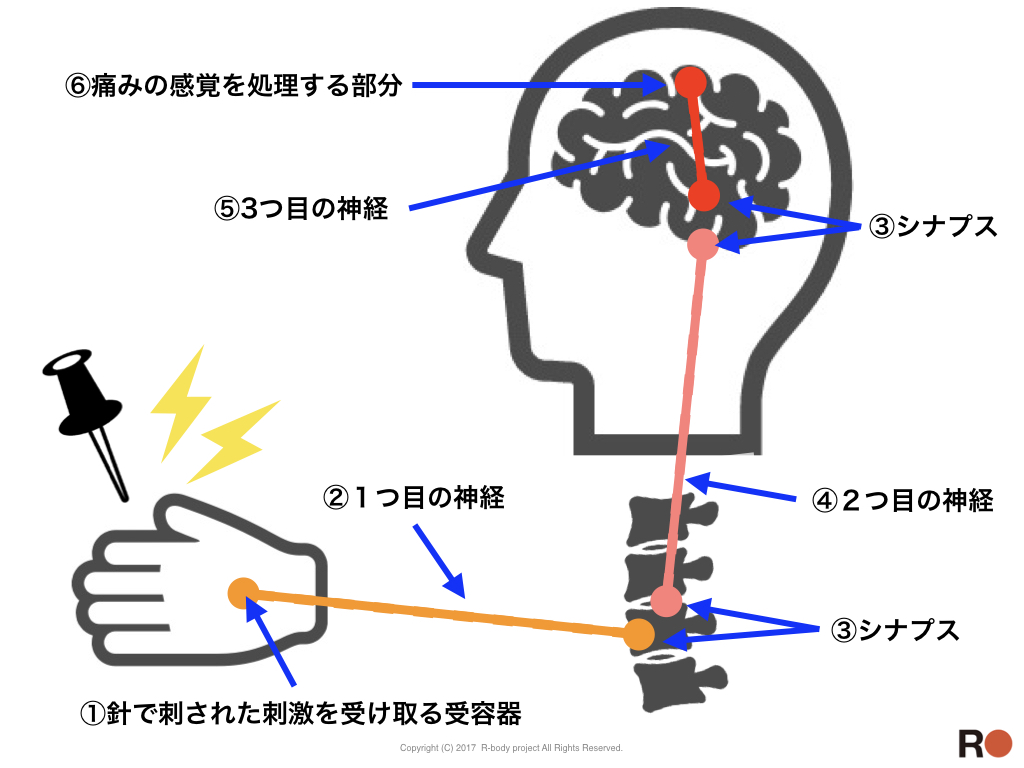
まず、画鋲などが指に刺さると、
「①感覚受容器」とよばれる皮膚の中にあるセンサーが、
その刺激を受け取ります。
そして、感覚受容器は受け取った刺激を電気信号に変換し、
受容器と背骨の中とをつなぐ「②1つ目の神経」に流します。
流された電気信号は、神経の端にある、
「③シナプス」と呼ばれる器官で、
「神経伝達物質(難しいですが電気信号では無いものと思ってください)」
に変えられて神経の外に放出されます。
シナプスから放出された神経伝達物質を、
「④2つ目の神経」のシナプスが受け取り、
また電気信号に変えて・・・
とうことをくりかえし、
最終的には「⑤3つ目の神経」を介して、
脳みその中の「⑥痛みの感覚を処理する部分」に伝わるのです。
このようにカラダの中を調べていくと、
400年前にデカルトが説明したイラストのように、
情報を、1本の神経だけ脳みそまで伝えているわけではなく、
3本もの神経を介して伝えていることがわかります。
※デカルトについてはこちら↓
https://r-body.com/blog/20190317/3136/
画鋲で刺された刺激がどのように伝わるか、
なんとなくイメージが持てましたでしょうか?
次回は、これらの基礎知識をつかって、
痛みについて考察を深めていきます!
END:2019.04.07
END:2023.044.11 archive
ーーーーーーーーーーーー
店舗情報について
大手町店:https://r-body.com/center/otemachi/
柏の葉店:https://r-body.com/center/kashiwanoha/
