人類の歴史①
宮山 卓也上級Conditioning Coach
こんにちは!R-bodyの宮山です。
最近以下の本を読んでいるので、
その内容を一部紹介したいと思います!
『人体六〇〇万年史 上──科学が明かす進化・健康・疾病 (早川書房) 』
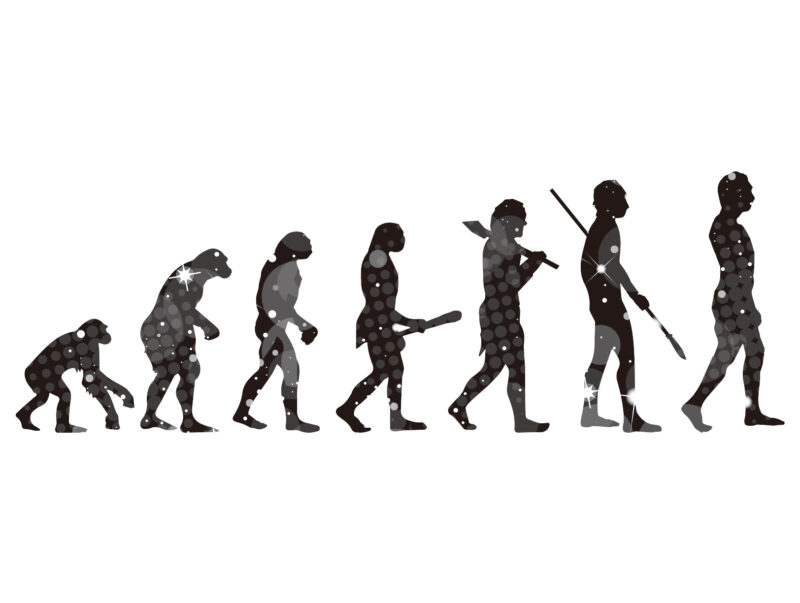
この本は人類の進化に関わることから
生活習慣病に関わることまで書かれてあり、
様々な視点から人類史を見ている本です。
まだ読んでいる途中ですが、
自分たちの祖先にあたる数百年前のことを想像しながら読むと、
非常におもしろく、決して他人事のようには思えない内容です!
それでは、
なぜ人類は二足歩行となったのかを抜粋したいと思います。
これに関して確実な答えを知ることは不可能だけれども、
これまでに得られている証拠から最も現実味があるのは、
次のような考え方のようです。
ちょうど人類の系統とチンパンジーの系統が分岐したころに
大規模な気候変動が起こったようです。
そんな状況でできるだけ効率的に食料を探し、
手に入れるのに有利だったことから、
定期的に立ち上がって行動する初期人類の行動が生まれた、とのことです。
(チンパンジーと人間は97%の遺伝子コードが一致すると言われているようです。細かい話は除きます。)
気候変動が起きたことで、生活圏周囲の森が縮小し、
当時食べ物としていた果物を手に入れるために
遠くへ出かける必要に迫られ、
その移動を効率良くするため、そして果物をかき集めるのを
容易にするために二足歩行が発達したと考えられています。
まず二足で立つということは、
ぶら下がっている果物に手を伸ばして取りやすい姿勢と言え、
オラウータン、チンパンジーや一部のサルも
同様にして果物を取っています。
そして二足で歩くということに関してですが、
二足歩行は四足歩行よりもエネルギーを節約できるようです。
チンパンジーなどが行う四足歩行(ナックル歩行)は
エネルギー的にコストが高く、
実験室でチンパンジーに酸素マスクを装着させて
ルームランナーを歩かせてみたところ、
その消費エネルギーは人間が同じ距離を歩いた場合の4倍にも達していたようです。
こうした差が生まれるのは、
チンパンジーの脚が短いこと、身体が左右に揺れること、
腰と膝を常に曲げて歩くことが原因で、
結果として、チンパンジーはつんのめったり転んだりしないように、
背中、腰、太ももの筋肉を収縮させるから
多大なエネルギーを絶えず消耗することとなります。
チンパンジーが1日にわずか2~3キロほどの
比較的短い距離しか移動できないのも、
上記の理由から不思議ではないと言えます。
人間なら同じエネルギー量で8~12キロは移動できるようです。
つまり二足歩行ができるということは、
気候変動により食料が分散した時代に
実に有利な適応だったであろうと言えるのです。
人間の骨盤の形状も、二足歩行に適応した形に進化してきたようです。
四足歩行のチンパンジーのそれとは形状が異なります。
ここまで読んでていて最近思うことは、
そもそも人の骨格は長時間椅子に座ったり、
パソコンと向き合ったりするために進化してきたわけではないので、
同じ姿勢でいたりすると、肩が凝ったり身体が硬いと感じたり、
何か不具合が出てくるのは当然だなと思いました。
脳が異常に発達した人間は、
身体的な進化の後に文化的な進化を遂げてきました。
今更昔の人類のような生活をして健康を取り戻しましょう、
なんていうのは不可能なので、
やはりそもそもの身体の構造から考えても、
身体を運動によって整える「コンディショニング」は
重要だなぁ・・・と改めて感じる今日この頃でした。
また読み進めたら続編を載せたいと思います!
この本は大手町店の本棚にあるので、
興味のある方はぜひ一度手に取ってみてください!
END:2019.07.14
END:2023.03.01 archive
ーーーーーーーーーーーー
店舗情報について
大手町店:https://r-body.com/center/otemachi/
柏の葉店:https://r-body.com/center/kashiwanoha/
