人体の歴史③ 〜なぜ虫歯ができるのか〜
宮山 卓也上級Conditioning Coach
こんにちは!
R-body projectの宮山です。
以前もご紹介した以下の本から、今回も内容をピックアップしてお届けします。
『人体六〇〇万年史 上──科学が明かす進化・健康・疾病 (早川書房) 』
過去のコラムはこちらから
https://r-body.com/wordpress/blog/20190714/3953/
https://r-body.com/wordpress/blog/20210129/7008/
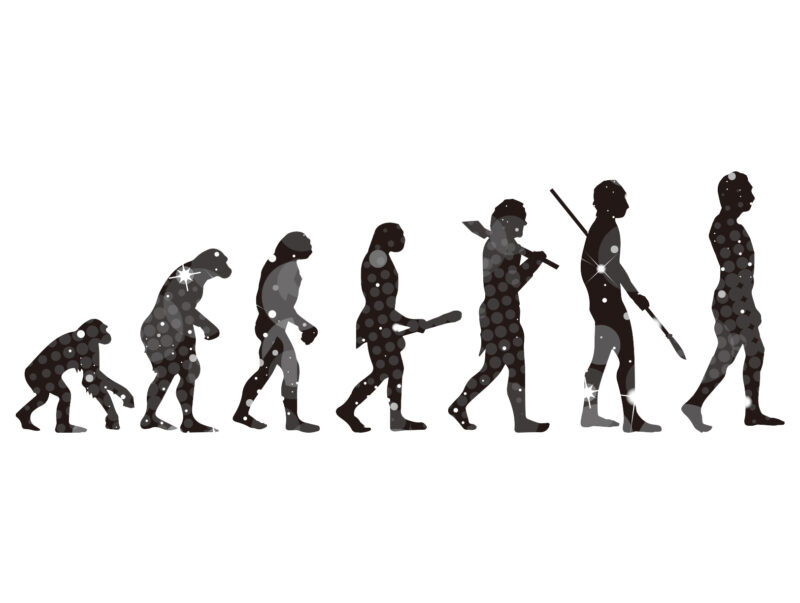
今回は、「なぜ虫歯ができるのか」という内容です。
この本では、
虫歯は進化的ミスマッチ病だということを言っています。
ミスマッチ病とは、
人は身体的な進化と文化的な進化があり、
それらがかけ離れてしまうことで起こる病気、ということです。
虫歯についてですが、
口内にいるほとんどの細菌は天然の無害のものですが、
ごく少数の種が食物に含まれる澱粉や糖を餌として使う際に、
そこから放出された酸が、歯を溶かして穴を開けるそうです。
虫歯が広まったのは農業が開始された後のことで、
急激に増加したのは19世紀と20世紀と言われています。
一方で穀類などを主食としてない類人猿は、
虫歯になることはめったにないそうです。
つまり、
もしも私達が本当に虫歯を予防したいのなら、
糖と澱粉の摂取を劇的に減らすことが必要とのことです。
しかし、
農業が始まって以来、
世界の人々の大半は、摂取カロリーの大部分を穀類に頼ってきており、
澱粉、糖を減らす虫歯を本当に予防できる食生活にするのは不可能に近いですね。
要するに、
虫歯は私達が手軽にカロリーを得るための代償のようなもの、
とこの本では言っています。
この本を読むと、
便利になる一方で、
人間は身体的なことに関してはトレードオフをしながら文化的な発展をしてきているのだ
という認識を僕は持つことができました。
温故知新と言いますか、
過去のことを知ることでモノの見方が変わってきますね。
また次回も、人体の歴史について触れていきます!
END:2021.05.28
